医師不足を助ける新しい資格「医師助手」の期待度
2024年4月に始まった医師の働き方改革を先取りし、2010年から改革に取り組み成功を収めているのが、亀田総合病院スポーツ医学科だ。
医師に代わって診察の一部を支援できる、アメリカの国家資格「PA(Physician Assistant:医師助手)」を院内資格としてアレンジし、医師が医師本来の仕事に専念できる環境を作った。
はたしてPAとはどんな仕事なのか――。
PAとして活躍する看護師
「そのしびれは、膝の近くを走る神経にボルトが当たっているからだと思います。ボルトを抜いたあとに、症状が緩和する方が多い傾向にありますよ」
亀田京橋クリニック(東京都中央区)のスポーツ医学科の外来診察室で、翌月に手術を控えるAさんへの術前説明が行われていた。
PAで看護師の山田凌大(りょうた)さんは、医師の指示・監視下のもと、膝の状況を確認する触診を行い、レントゲンやMRIの画像をAさんに見せながら、手術内容の説明や、入院から退院までのスケジュールや注意事項などを詳しく伝えていく。
患者には専門用語の羅列では伝わらない。「会話を通してどこまで理解できているかを確認しながら、言葉を選んで伝えていくことを心がけている」と山田さん。

Aさん(右)に手術の説明をする山田さん。数年来の関係性で和やかな空間があった(写真:筆者撮影)
スムーズな手術の進行を目指す
朝8時30分。
病院の手術室には、第一助手として加藤有紀医師の前で手術をサポートする山田さんの姿があった。PAは山田さんを含め3人(取材当時。現在は4人)が在籍。手術がある日は加藤医師が手術室に入るまでに以下の役割を分担し、スムーズな手術の進行を目指す。
・その日の手術全体のスケジュールの確認・調整・手術中に確認するレントゲンやMRIなどの画像データを選んでモニターに表示する
・使用する手術機材の確認
・手術室看護師への教育的関わり
・手術室に入室した患者さんとのコミュニケーション
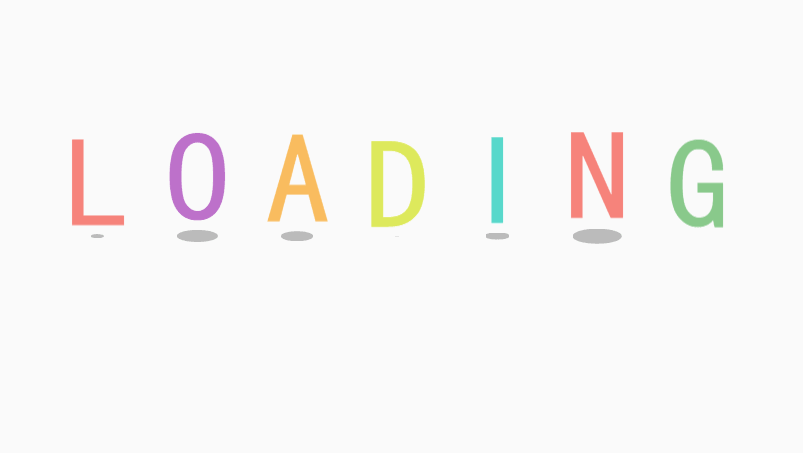
手術開始までにレントゲン写真やMRI画像を選定する山田さん(写真:筆者撮影)
「お願いします」という加藤医師のかけ声で、手術が始まった。
PAたちは次に加藤医師がどのような動きをするのかを先読みし、必要なタイミングで吸引したり、透視のモニターが見やすいように立ち位置をずらしたり、術野が見やすいように傷口を固定したり。加藤医師の手が止まることなく、あうんの呼吸で粛々と手術が進む。静かななか、心電図などのモニターや電気メスの音だけが響く。
これまでは医師が行っていた術後の患者や家族への説明、サマリーと呼ばれる手術内容や経過の記載は、医師の指示のもとにPAが担う。それにより、加藤医師は次の手術に備えたり、別室の手術に参加することが可能になった。
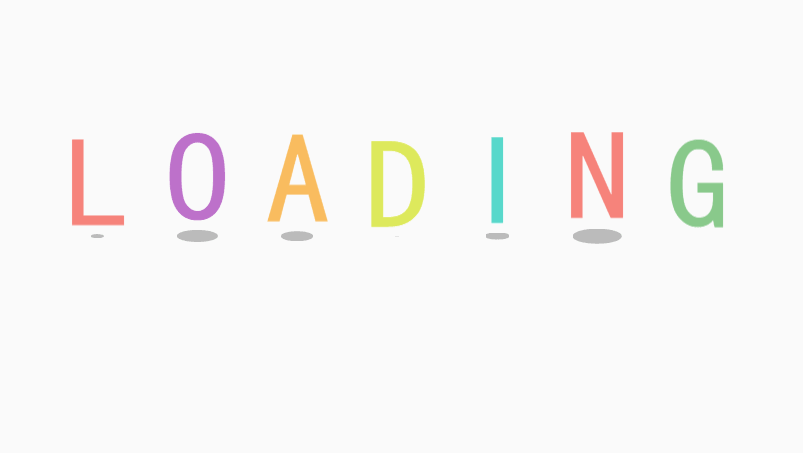
医師の指示のもと電子カルテにサマリーを記載する山田さん(写真:筆者撮影)
安心感につながっている
午後、山田さんは加藤医師と整形外科の病棟に向かい、膝の手術を終えて退院が近いBさんの病室を訪ねた。術後の画像をBさんと一緒に確認したあと、通院のスケジュールや退院後の注意点などを伝える。
トライアスロンを趣味にするBさんが、「退院後はいつから走っていいですか?」と聞くと、理由を話したうえで、「1カ月は安静にして、その後少しずつ動かしていきましょう」と説明。Bさんは競技復帰までのイメージをつかめたようだった。
「話を聞いてくれる人がいることが安心感につながっている。(山田さんには)わからないことを何でも聞けるし、それに答えてくれる頼りになる存在」とBさんは話す。
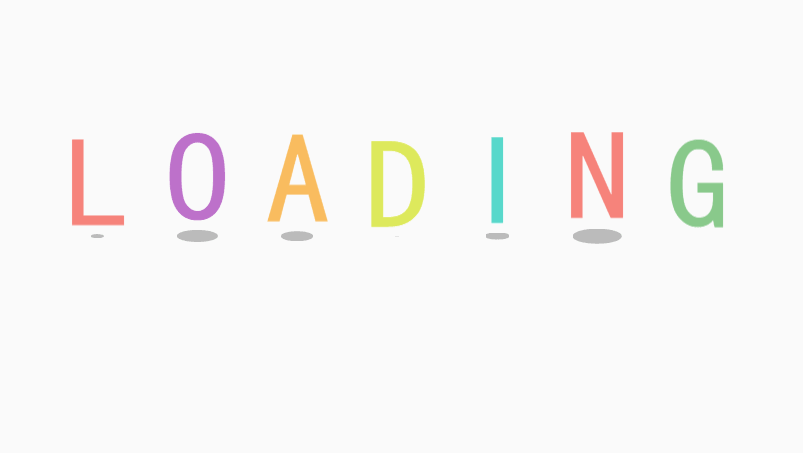
Bさん(左)に術後の経過や退院後の生活について話す山田さん(中央)と加藤医師
PAは1960年代、医師不足が社会問題となったアメリカで始まった。その後、医師の監督下で診察・検査・処方などを行う専門職として地域医療を担い、その存在価値が広く認知されるようになった。
日本でも医師の働き方改革などを受け、2010年頃からPA導入に向けた議論が厚生労働省などで行われている。しかしながら、具体的な業務の検討が必要とされているものの、医師以外の者が医行為を行うことへの懸念や安全管理、診療報酬上の配慮が必要なことから、現在までに制度の創設には至っていない。
亀田総合病院にPAが院内資格として導入されたきっかけは、2009年にスポーツ医学科が整形外科から独立したことにある。
開設当初は少人数で対応可能な手術が中心だったものの、患者数の増加に伴い、手術件数はもちろん、紹介状の返信やサマリーの作成など診療以外の業務が膨れ上がり、医師たちを圧迫。さらなる診療拡充を目指していた大内洋医師(同科主任部長)は、研修医以上の知識を持った看護師によるサポートが必要だと考え、院内にPAを配置しようと動き始めた。
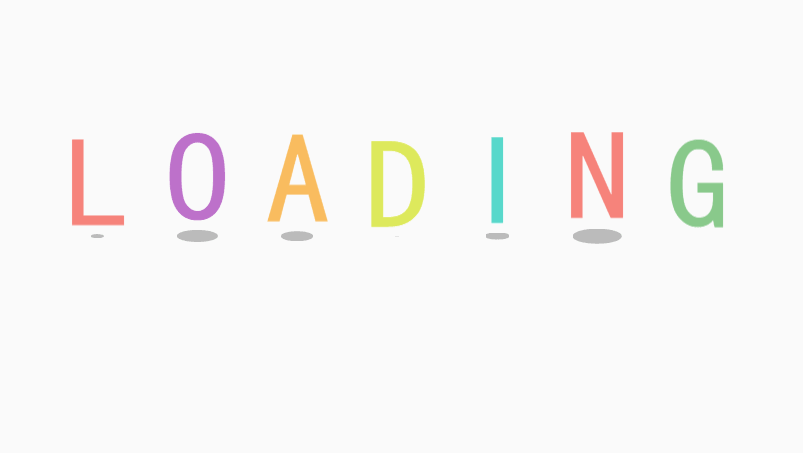
PA導入時を振り返る大内スポーツ医学科主任部長(写真:筆者撮影)
PA誕生までの道のり
PA創設にあたり、大内医師は前の職場で出会った理学療法士の市川顕さんに声をかけた。市川さんはPAの業務をするうえで必要な准看護師の資格を取得したうえで、2010年4月、スポーツ医学科のPAとして働き始めた。
だが、日本に存在しない資格であるPAにどこまでの業務を任せられるか。「そこを定義するのが難しかった」と市川さん。
PAに必要な看護師や准看護師の資格は、法律では「診療の補助」と「療養上の世話」と定義されており、その範囲を超えることはできない。院内での協議を重ね、詳細な業務範囲を少しずつ広げていった。
一方、市川さん自身にも医学的な知識や、診察に必要なスキルが不足していた。そこで、たくさんの書籍や論文を読んだり、学会などに参加したりするなど猛烈な勉強の末、医師と共通言語で会話できるレベルになった。
今では研修医や看護師などへの指導も行うようになり、PAのレベルの向上とともに、周囲からの信頼はさらに高くなっている。
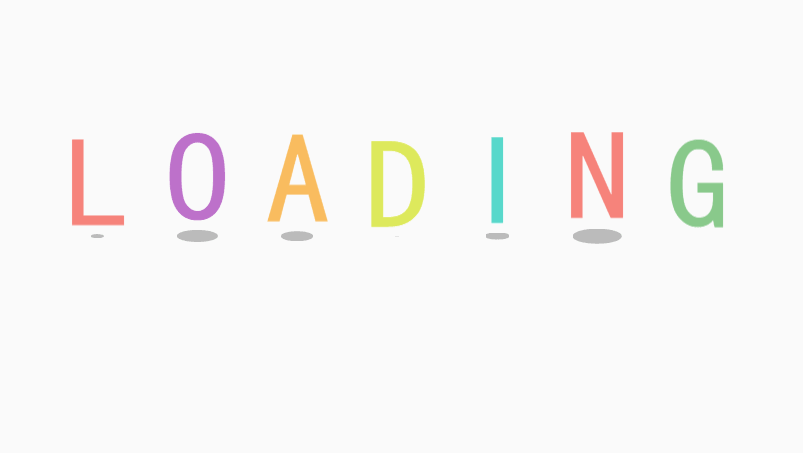
山田さんが進行を務める多職種カンファレンスの様子(写真:筆者撮影)
PAの活躍で手術件数の増加
そして今やPAは、医師の働き方改革のキーパーソンでもある。
2016年に加藤医師が着任した当初、患者数を増やそうと夜遅くまで外来を開けていたため、医師やPAは夜9時頃まで働くことが常態化していた。だが今は、その頃よりも患者数は圧倒的に多いものの、終業時間の17時には仕事を終わらせている。
「そのぶん仕事が凝縮されて、走り回ることも多いですが。1つひとつの診察や治療、手術の質を担保することは絶対なので、PAが外来、手術部、看護部などのさまざまな部署に働きかけ、診療環境の拡充、次の手術の迅速な準備、病棟との情報共有を行っています。スムーズに進めようとするサポートが重要です」(加藤医師)
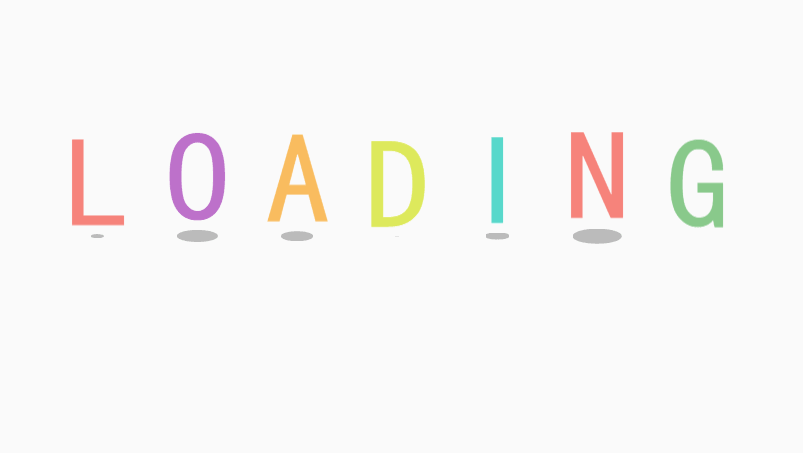
PAの山田さん(左)、加藤医師(中央)、市川顕さん(右)(写真:筆者撮影)
さらに、PAの教育が進み、年間200件だった手術件数が500件に増えたタイミングで業務内容を広げた。スポーツ整形外科の専門知識を有したPAが積極的に患者さんと関わることで、不安の解消や治療上の些細な変化をキャッチすることが可能になった。
また、各部署と密なコミュニケーションを図り、「ハブ」の役割を担ったことで、同科全体は忙しくなったにもかかわらず、患者満足度と院内におけるPAの認知度が上昇するという好循環が生まれた。
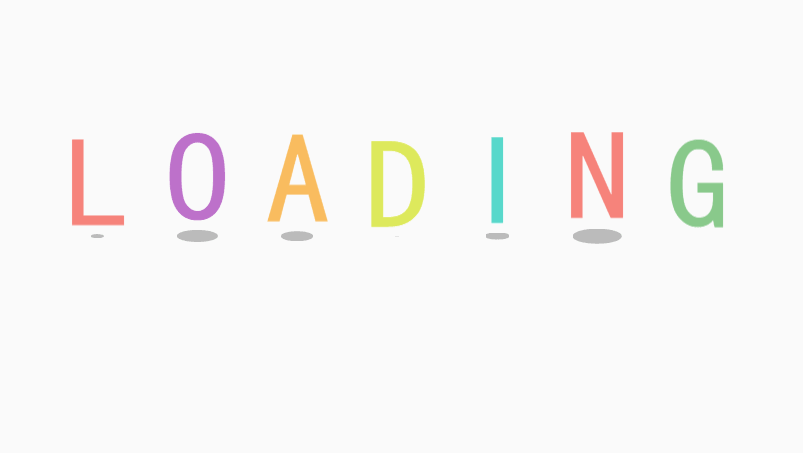
数日後に手術の見学を予定している理学療法士(左)に手術方法の説明をする山田さん(写真:筆者撮影)
それによって、スポーツ医学科は院内でも大きく収益を出す科に進化し、他科・他部門のスタッフからも注目されるようになった。さらに、看護師の新たなキャリアとしても注目されるという副産物も生み出した。
医師と患者、他の職種をつなぐ
医師と患者だけでなく、医師と他の職種をつなぐPA。
一方で、看護師とPAをどうすみ分けるのか、難しい面もある。実際、本来は看護師もやっていいことであっても、「PAがやるだろう」という理由で看護師がやらない業務も出てきていると、山田さんは懸念している。
お互いが持つ情報を共有し、さらなる多職種連携強化を目的としてPAが主体となり、看護師・医師・理学療法士などによる多職種カンファレンスが行われるようになった。
「PAは新たな看護師のキャリア。入院中だけでなく、退院後やその数年後を見据えて、患者さんに必要なケアは何かと考えながら関わることが、やりがい」と山田さん。
PAが同院で必要不可欠な存在になったことをモデルとし、患者の回復・健康増進に関わる職種として社会に広く認知され活躍することで、医師の働き方改革以降も質の高い医療が継続されるだろう。